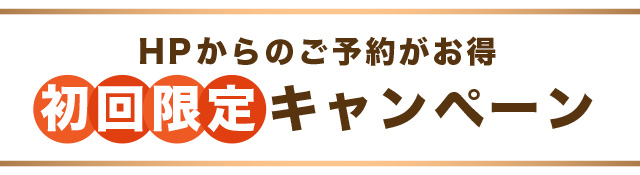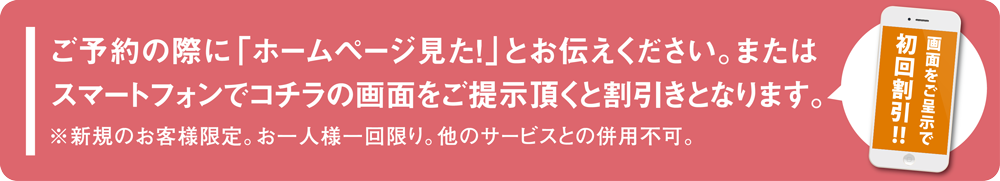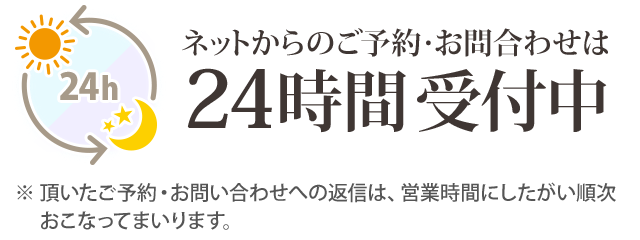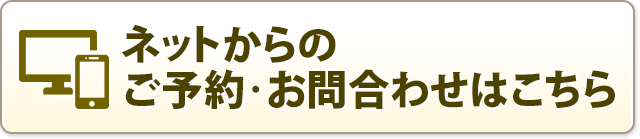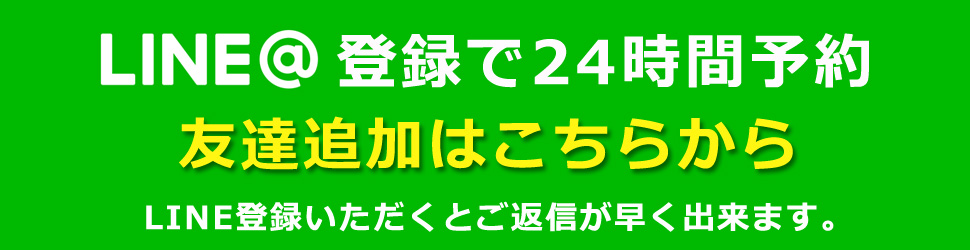はじめに
「猫背を直したい」「姿勢が悪いのが気になる」という方は多いですが、見た目だけでなく自律神経のバランスにも深く関わっていることをご存じでしょうか。
姿勢が崩れると呼吸が浅くなり、体は交感神経優位の“緊張モード”に入りやすくなります。
今回は、整体の視点から猫背と自律神経の関係、そして改善のためのポイントをご紹介します。
猫背と自律神経のつながり
呼吸が浅くなる
猫背になると胸が圧迫され、肋骨や横隔膜が十分に動きません。
理想は「吸う量=吐く量」ですが、猫背では吸える量が減り、結果的に吐く量も減ります。
吐く動作は副交感神経を働かせるスイッチですが、この動きが弱くなることでリラックスしにくい状態になります。
背骨の動きが硬くなる
自律神経は背骨(脊柱)を通る神経から全身に枝分かれしています。
背骨の柔軟性が低下すると、神経や血流の働きも低下しやすくなります。
特に胸椎(背中の中央あたり)の硬さは、呼吸の深さと直結します。
猫背が引き起こす悪循環
猫背で胸郭(胸のかご)が狭まる
吸気量が減り、吐く量も減少
副交感神経が働きにくくなる
交感神経優位の状態が続く
肩こり・頭痛・疲れやすさ・不眠などの不調が出やすくなる
整体での猫背改善アプローチ
背骨・胸郭の動きを回復
胸椎の伸展(反らす動き)を出す施術
肋骨まわりの筋肉(肋間筋・小胸筋)を緩める
背骨全体のしなやかさを取り戻す
呼吸のサポート
横隔膜の動きを促す施術
肋骨が開きやすくなるようなストレッチ指導
姿勢維持の筋肉を整える
腹部のインナーマッスル(腹横筋・多裂筋)
背中の姿勢保持筋(菱形筋・脊柱起立筋)
セルフケアのポイント
自宅でもできる簡単な猫背対策をご紹介します。
胸を開くストレッチ
両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せながら胸を開く
深呼吸を3回繰り返す
壁スクワット
背中を壁につけて立ち、膝を軽く曲げてゆっくり呼吸
背骨の自然なS字カーブを意識する
腹式呼吸
鼻から3秒吸い、7秒かけて吐く
肋骨が横に広がる感覚を意識
東洋医学的な補足
首や肩のコリが強い方には、東洋医学でいう「天柱(てんちゅう)」「風池(ふうち)」といった首の後ろのポイントが硬くなる傾向があります。
これらは自律神経や頭痛のケアにも関連があるとされ、整体では優しい圧やストレッチで緩めます。(※鍼灸ではなく手技で対応)
まとめ
猫背は呼吸を浅くし、副交感神経が働きにくくなる
整体では背骨・胸郭・横隔膜を整えて呼吸を深くするアプローチが有効
セルフケアは胸を開くストレッチや腹式呼吸がおすすめ
次回は「背骨と自律神経の関係」を詳しく解説します。